
ベビー用品の準備も進んできたけど、次に気になるのは…やっぱり子どもの将来のお金のこと。「学資保険に入らなきゃ」って漠然と思うけど、そもそも何が良いのか全然分からない…。
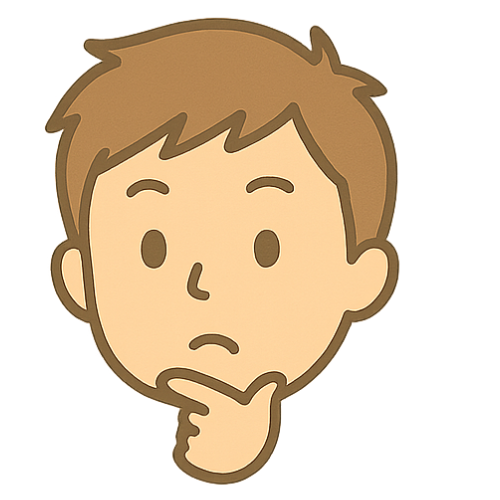
最近は「NISA」で貯める人も多いって聞くし、「学資保険は元本割れする」なんて話も…。一体、何を信じたらいいんだろう。ちゃんと調べておかないと、将来後悔しそうだ。
「子どもの将来のために、何かしてあげたい」
そう思うからこそ、教育資金の準備は絶対に失敗したくないですよね。
でも、お金の話は専門用語が多くて、正直考えるだけで疲れてしまう…。その気持ち、痛いほど分かります。
この記事は、そんなあなたと私自身のために、「学資保険」と「NISA」という2大選択肢について、どこよりも分かりやすく、本音で比較したものです。
この記事を読めば、あなたの家庭に本当に合った「お金の育て方」のヒントが、必ず見つかります。
そもそも「教育資金」って、全部でいくら必要?
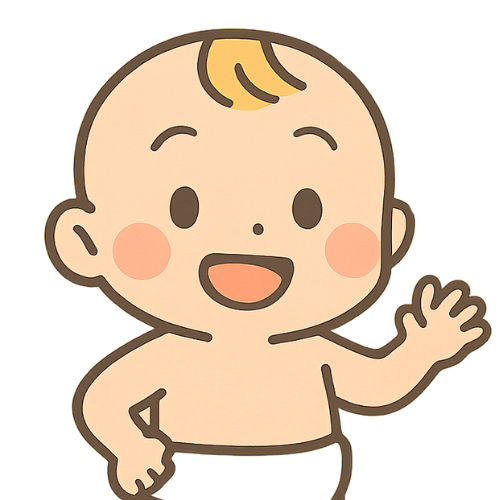
パパ、ママ、ありがとう!僕が大きくなるまでに、実はこんなにお金がかかるんだ。知っておいてくれると、僕も安心だな!
具体的な計画を立てる前に、まずはゴールを知っておきましょう。子ども一人を育てるのにかかる教育費の目安は、進路によって大きく変わります。
- すべて国公立の場合:約1,000万円
- すべて私立(理系)の場合:約2,500万円
※文部科学省、日本政策金融公庫のデータを基にした目安です。
この数字を見て、「そんなに!?」と驚かれたかもしれません。でも大丈夫。今からコツコツ準備を始めれば、決して不可能な金額ではありません。
「学資保険」のメリット・デメリットを本音で解説
まずは、昔からの王道である「学資保険」について、良い点と注意点を正直に見ていきましょう。
学資保険のメリット(良いところ)
- 強制的に貯められる:一度契約すれば、毎月自動的に引き落とされるので、貯金が苦手な人でも着実に貯蓄できます。
- 親の万が一に備える「保障」がある:契約者(親)が亡くなったり、高度障害状態になったりした場合、それ以降の保険料の支払いが免除され、満期金は予定通り全額受け取れます。これはNISAにはない、保険ならではの大きなメリットです。
- 生命保険料控除が使える:年末調整や確定申告で、所得税・住民税が少し安くなります。
学資保険のデメリット(注意点)
- あまり増えない(インフレに弱い):返戻率(払ったお金に対して戻ってくるお金の割合)は103%~108%程度が一般的。銀行預金よりは良いですが、物価が上がると、お金の価値が実質的に目減りしてしまう「インフレ」に弱いのが最大の弱点です。
- 途中解約すると元本割れする:大学入学などの満期を迎える前に解約すると、払った金額よりも少ないお金しか戻ってこないことがほとんどです。
学資保険が「向いている人」と「向いていない人」
【結論】あなたはどっち?
▼学資保険が向いている人
- 「とにかく貯金が苦手で、強制力がないと貯められない…」という人
- 「万が一の時の保障を手厚くしたい」という人
- 「投資は怖い、元本割れのリスクは絶対に避けたい」という堅実派の人
▼学資保険が向いていない人
- 「保障は死亡保険などで別に備えている」という人
- 「物価上昇に負けないよう、効率的にお金を増やしたい」という人
- 「ある程度のリスクは許容できる」という人
もう一つの選択肢「つみたてNISA」って何が違うの?
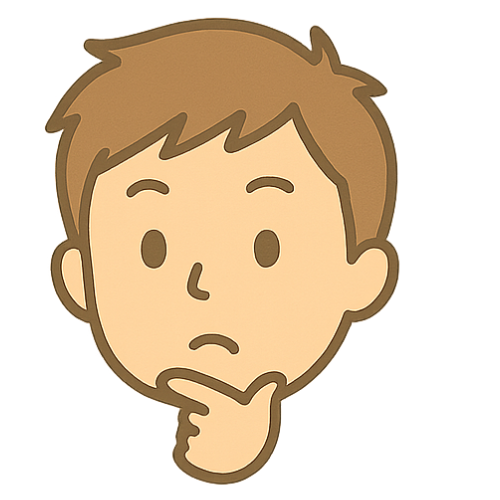
最近よく聞く「NISA」は、学資保険と何が決定的に違うんだろう?
NISAは、国が作った「個人投資のための税金優遇制度」です。教育資金準備でよく使われる「つみたてNISA」と学資保険の違いを表にまとめました。
| 学資保険 | つみたてNISA | |
|---|---|---|
| 目的 | 貯蓄+保障 | 資産運用(投資) |
| お金の増え方 | 契約時に決まっている(低い) | 運用実績による(高い可能性も) |
| 元本保証 | あり(満期まで続ければ) | なし |
| 保障機能 | あり | なし |
| 引き出しの自由度 | 低い(途中解約は損) | 高い(いつでも引き出せる) |
簡単に言うと、ローリスク・ローリターンで保障付きなのが「学資保険」、ミドルリスク・ミドルリターンを狙えるのが「NISA」です。
【わが家の結論】プロに相談して、オーダーメイドの計画を立てることにしました
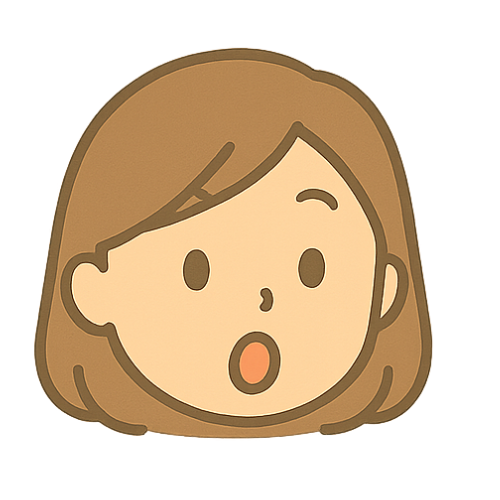
正直、ここまで調べても、じゃあ我が家の場合はどっちがいいの?って、また迷っちゃった…。それぞれの家庭の収入や考え方によって、正解は違うんだよね。
そこで、私たちが取った次の一手が「無料のFP(ファイナンシャルプランナー)相談」でした。
FPとは、ひと言でいえば「お金の専門家」。私たちの家計の状況や、将来どうしたいかなどをヒアリングした上で、「あなたの家庭の場合は、学資保険とNISAをこのくらいの割合で組み合わせるのがベストですよ」といった、オーダーメイドの計画を提案してくれます。
何より、「誰に相談していいか分からない」という漠然とした不安が、「この人に聞けば大丈夫」という安心感に変わったのが、一番の収穫でした。
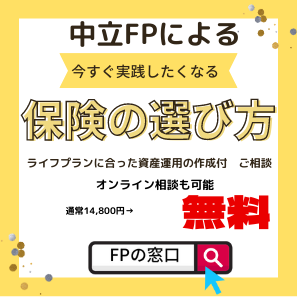
まとめ:お金の不安は「知ること」と「相談すること」で軽くなる
教育資金の準備に、全ての人に当てはまる「唯一の正解」はありません。
大切なのは、まず学資保険やNISAといった選択肢のメリット・デメリットを「知る」こと。そして、自分たちだけで抱え込まず、専門家に「相談する」こと。
この2つのステップを踏むことで、漠然としたお金の不安は、必ず「未来への希望」に変わっていくはずです。まずはその第一歩を、今日踏み出してみませんか。

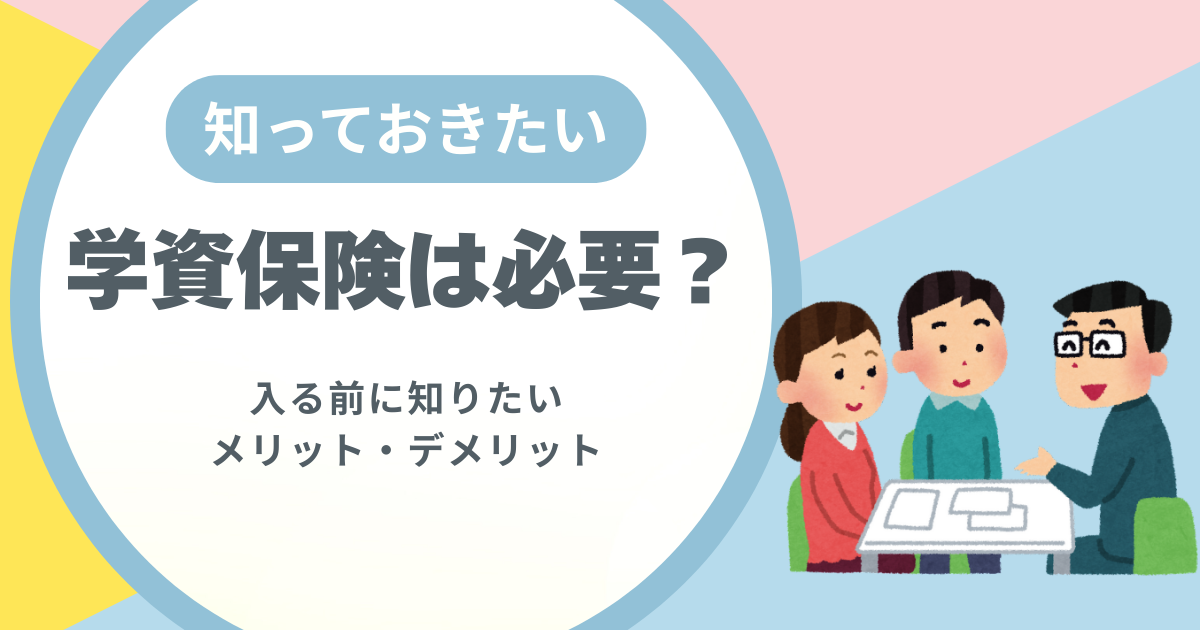
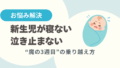
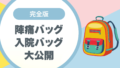
コメント